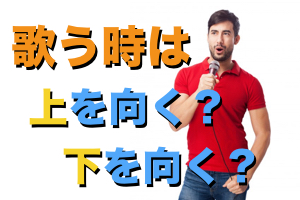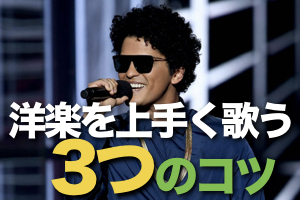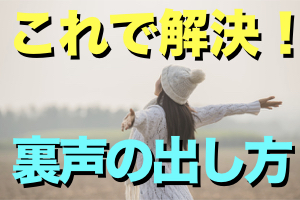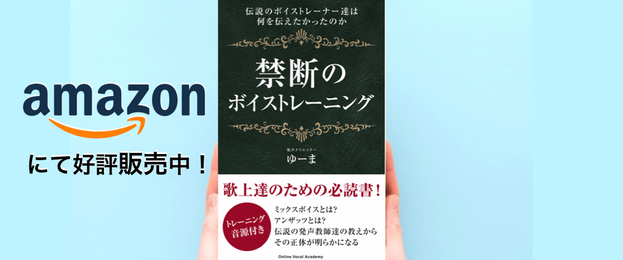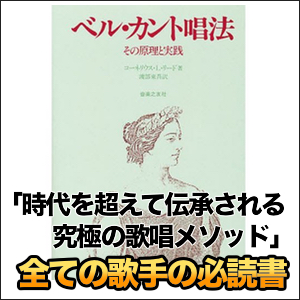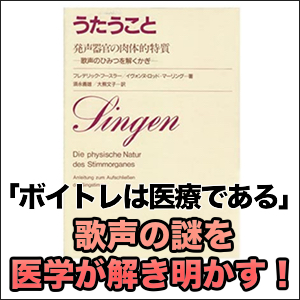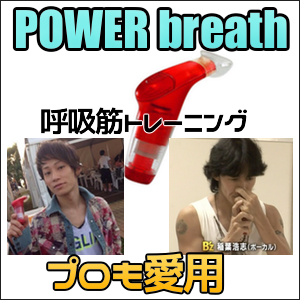皆さんこんにちは!
今回は『共鳴』について新たな視点から書いてみたいと思います。
フースラーや、リードも『声帯より上方を意識するあまりに肝心なことを見失っている』という趣旨を述べていますが、その1つが「共鳴」です。
共鳴により、音を増大させる方法を追求するあまりに声に関しての本質を見失ってしまうシンガーがとても多いです。
ですので今回はその辺りについての考察を述べてみたいと思います!
『声帯より上方のことばかりに気を取られてしまうこと』に、フースラーも、リードも警笛を鳴らします。
それは『共鳴』をはじめとする声帯原音以外の現象の操作を指します。
それらは大事なことですが、声帯そのものの間接操作や筋力のレベルアップを端に追いやってしまうと本質は見えなくなります。
— ゆーま/ボイトレ本執筆中♪ (@MVS_music) 2019年7月2日
では、いってみましょ〜!
共鳴とは
これは既に3年ほど前にこちらのyoutube動画で説明していますが、『共鳴』とは声帯で鳴った原音が身体の共鳴腔で増大されることを指します。
例えると、鍾乳洞のように潤った硬い空間で音が反響するようなイメージです。
この反響音をしっかりと感覚的にコントロールしながら音を増大させることが共鳴による音量増大法です。
共鳴増大法の限界点
ここで先に述べておきたいことは、僕が『共鳴』を軽く見ているということではないということです。
共鳴をしっかりと感じて音をコントロールすることは、とても大切なのですが、その一歩手前にはまだ大切なことがあるのです。
それは『声帯原音自体の音量』です。
ここで、例えを1つ。
同じ大きさの鍾乳洞で2人が交互に手を叩いたとします。
その時に、2人の手を叩く音自体の大きさが違ったとすると響く音量も違ってきます。


これは手を叩く音自体(原音)に差があるために、同じ大きさの空間では響く音量にも差が生まれたということです。
さて、話を戻します。
身体の共鳴腔は、その空間の絶対値や、増大させうる共鳴量の絶対値には上限があります。
頭部にある共鳴腔(鼻腔や、副鼻腔)は鍾乳洞と同じく骨組織で形成されているため大きさを増大させられません。
イコール、音量増大には、やはり絶対値が用意されています。
では、その絶対値をどうやって破るのか?
それは、先程の2人の手を叩く音と同じように原音を強くするのです。
原音を強くすることができれば、それに応じて共鳴腔の持つ絶対値まで音量を増大させ続けられます。
共鳴と原音が引き離せない関係を構築している以上、原音の音量レベルを引き上げられれば共鳴腔の持つ絶対値も引き上がったようなものなのです。
原音の問題を解決しないシンガー達
はじめに書いたリードとフースラーの警笛は、このようなことでしたね。
『声帯より上方を意識するあまりに肝心なことを見失っている』
これは、そもそも原音自体に全く意識が向いていないために、現時点での原音の音量や、声帯の間接操作テクニックのレベルのまま、共鳴や、その他の方法によって歌声をどうにかしようとしてしまうシンガーに向けての警笛です。
共鳴1つとってみても、そこには絶対値が存在してしまう以上、絶対に超えられない壁に向かって突っ込んで行くようなものです。
そして、その壁を無理に突破しようとすると、全てのリスクは容赦無く『声』に返ってきます。
誰が聴いてもイビツな声質、細く硬い金切り声、全く操作できそうにない硬直した声、揺れ声、種類は数え切れません。
そのような声の持つ特徴は全て、歌っているシンガーが感じるフィーリングが悪いのです。
断言しますが、発声の際のフィーリングが悪い場合、たとえ「それでOK!」とトレーナーに言われても間違っています。
シンガー自身が体感に違和感を感じることは、それほどまでに信じて良いことなのです。
自分自身の声や感覚を客観的に見ることも大切にしてください。