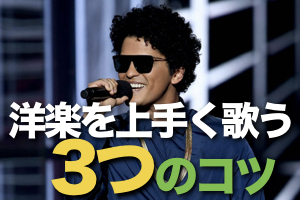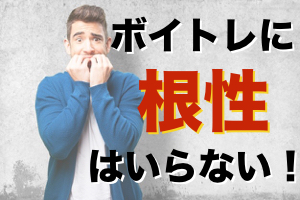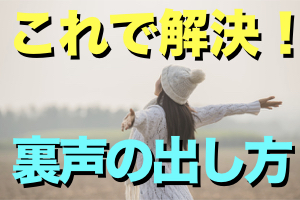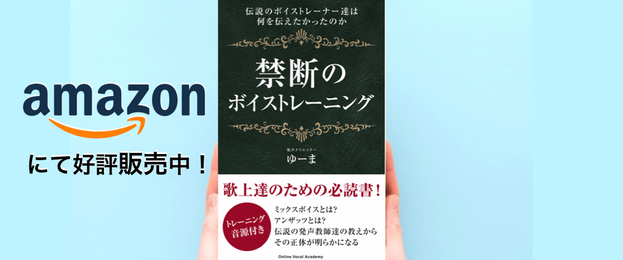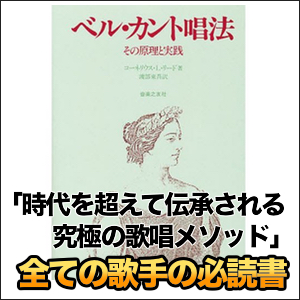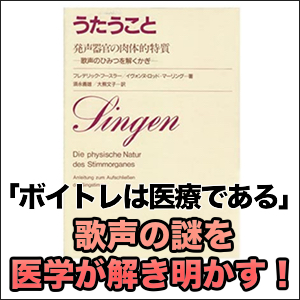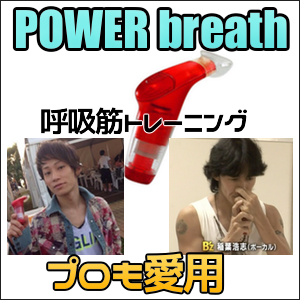皆さんこんにちは!
今回のテーマは先日ツイートした内容で『裏声がなぜ重要なのか?』です。
声帯の伸展動作は主に裏声発声に重要ですが、ピッチの安定にもかなり重要です。
伸展動作が上達するとともに地声発声の音程も以前より安定し始めます。#ボイトレ #ボイストレーニング #歌
— ゆーま/ボイトレ本執筆中♪ (@MVS_music) December 5, 2019
もちろんボイトレは、ただ裏声発声だけをひたすらに行えば良い訳ではありませんが一つの重要なトレーニングであることは確かです。
地声音域が狭い方や、ブレイク周辺になると喉が苦しくなるような方には、かなり重要な内容です。
では、いってみましょ〜!!
裏声声区の持つ威力
『裏声』を簡単に説明すると声帯の伸展作用です。
この裏声もスカスカに抜けた裏声から、発達した発音の明瞭な裏声まで個人差は様々です。
かなり簡潔に書くと、裏声を発声する時というのは声帯を包み込んでいる甲状軟骨やそれにジョイントしている輪状軟骨、舌骨、披裂軟骨などが立体的に動き出します。(僕はこのような軟骨の集合単位を「ボイスユニット」と呼んでいます)
要は、安定した裏声発声では、声帯を上方から見ただけの2次元的な伸張という動きに加えて声帯を囲んでいる軟骨も大きく動きながら3次元的に伸張を更に強度に行うというわけです。
このようにダイナミックに喉頭組織を扱う場面というのは実は裏声しか不可能です。
地声は基本的には大きく声帯を伸展させる必要が無いために閉鎖という2次元的な動きが殆どです。
そのために地声でブレイク周辺に差し掛かったのにも関わらず声帯が伸展作用をスムーズに開始できないと声は一気に自由を失ってしまいます。
(僕のスクールではこれを「ロッキング現象」と呼んでいます)
この伸展作用というものは輪状甲状筋はもちろんその他の伸展に関与する筋群が立ち上がってくることを意味します。
伸展作用が不得意なシンガーの特徴
伸展作用が地声発声に組み込めないシンガーには大きく3つ特徴があります。
特徴①地声声区の中高音域で音程がフラット(♭)しているように感じる。または、音質が暗く感じる、重く感じる。
特徴②地声声区の高音域で決まった音質しか出せない。(殆どの場合「張り裂けぶ音」か「喉に詰まった音」)
特徴③声の裏返りが、めちゃくちゃハッキリしている。
逆に、声帯伸展の扱いが上達してくると徐々にではあっても上記のような症状が改善されていきます。
閉鎖のみでの音程操作に声帯の伸展が加わってくるのですから、もちろん音程も安定してきます。
まとめ
まとめ①声帯をダイナミックに運動させるのは裏声発声
まとめ②地声の音程操作にも伸展操作の上手さが関係する
まとめ③伸展操作が苦手なシンガーの特徴は大きく3つ
1、地声声区の中高音域で音程がフラット(♭)しているように感じる。または、音質が暗く感じる、重く感じる。
2、地声声区の中高音域で同じ音質しか出せない。(殆どの場合「張り裂けぶ音」か「喉に詰まった音」)
3、声の裏返りが、めちゃくちゃハッキリしている。